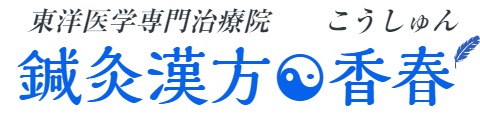ここでは鍼灸香春にて使われる鍼灸用小道具を紹介します。いわば、戦友です。
汎用太鍼(はんようたいしん)

香春では最初に使われることが多い、刺さない鍼です。刺せないこともないですが。
接触させることで身体を反応させる、低刺激の鍼です。
主に気候の悪影響を取り除くために使いますが、二種類の金属を使う特性上、その電位差を利用して
体感できない程度の微弱電流を通じさせることで、治療することもできます。
鍉鍼(ていしん)
こちらも刺さない鍼です。アルミ製で、自作品です。
接触させるだけなので、敏感な方に使うことが多いです。
刺絡(しらく)

一瞬だけ鍼を刺して数滴分の出血をさせるための方法を刺絡といいます。
本来は三稜鍼(さんりょうしん)という太い鍼を使うのですが、その類型がこちらになります。
左のキャップを、本体に取り付け、使った後はキャップ部分を廃棄します。
身体への不要な負担を減らして、効果を維持できます。
肘や膝が曲がらない、伸びないという症状、バネ指や腰痛などによく使います。
施術部位は主に手足の指先ですが、症状の程度によっては患部に用いることもあります。
棒灸

温灸の一つです。右側のホルダーに、もぐさで棒状に作った棒灸を差し込んで使います。
ピリピリした痛みや首肩の緊張が強い場合に用います。
眼精疲労や腰痛、膝痛などに評判がよいです。
温かくて気持ちがいいので当院でもよく好まれます。
温灸

棒灸と同じく、温める目的で使われます。棒灸よりも広範囲を温められます。
また中にセットするもぐさを増やすと火力を強くできるので、便利です。
右の大きな温灸器は蓋つきなので万一落としてしまっても安全です。
ご家庭で使う場合にお勧めしています。
お灸

一般的な、いわゆる“お灸”です。温灸とは違い、皮膚に直接お灸をすえるため、少し跡が残ります。
灸の跡は1日2日で消えるので問題はないのですが、やはり気になさる方もおられます。
そんな場合は灸点紙というシールの上から、効果を維持したまま、跡がつかないよう施灸できます。
その他お灸

当院では他にも右側の知熱灸、上側の台座灸(せんねん灸など)、左側のカマヤ灸を使っています。
これらは首肩こりの人に用いて、発汗を促したりします。
また、何回か繰り返してすえることで冷えを取り除いたりもできます。
吸い玉

吸い玉を陰圧にして身体に吸い付けて使います。首肩、腰、膝のコリや緊張を取り除きます。
細かいテクニックはいろいろとありますが、血行を促し筋疲労を回復させるのは同じです。
ただ陰圧にして吸い付けるため吸引痕が残ります。2~3日でほぼ消えますが、夏場は不人気です。
また、ぎっくり腰のような強度の腰痛などの場合、刺絡と組み合わせて出血させることもあります。
内出血して周囲の組織や器官を圧迫していることがあるので、出血させて圧迫を改善するわけです。
打鍼

お間にお腹に使います。お腹の硬くなっている部分(硬結)に上部の棒(打鍼用のはり)を当てて、
下部に見える槌で軽くたたきます。その振動で硬結を散らして緩めたり、
エネルギー(気や血液)を集めたり、追い払ったりします。
鍼だけでは動かせない頑固な硬結(積)に用いたりします。
芦屋 鍼灸 香春(こうしゅん)【JR芦屋徒歩6分】